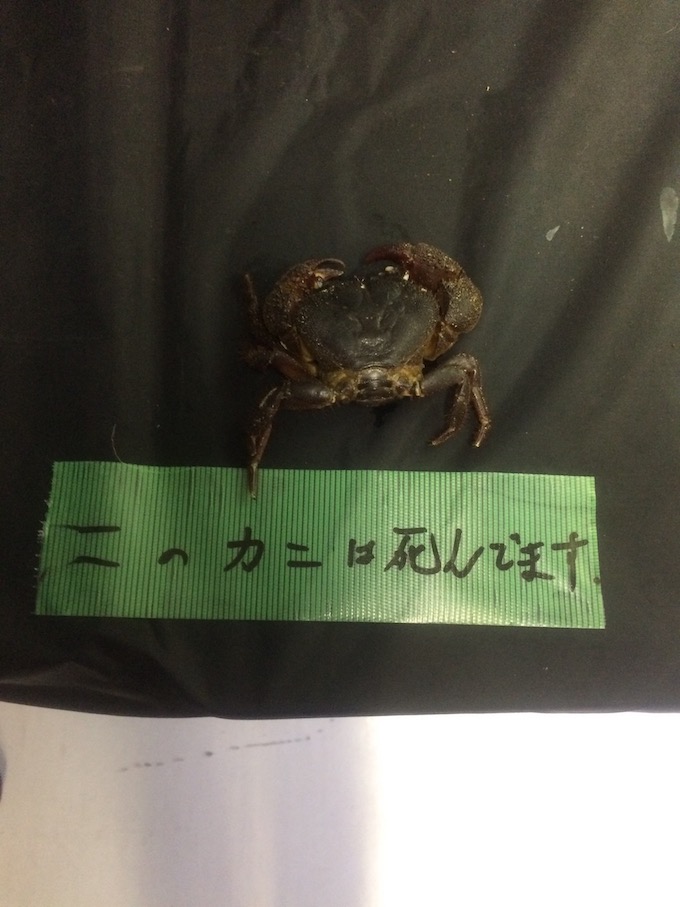読書の記憶というのは︱︱少なくともわたしの場合︱︱非常に頼りないもので、おもしろかった、つまらなかったという感想以外になにが思い出せるかといえば、書き出しがこんなふうで新鮮だった気がする、とか、クライマックスで突然わけのわからないことが起きて驚いたかもしれない、とか、ただただ自分が情けなくなるようなおぼろげな印象ばかりである。この書評を読み終えたときに「あ、これ、〈熊〉で読んだことがある」と思い出したことも、だから、なんの信用もできなかった。
堀江敏幸の作品に、「熊の敷石」という短編がある。彼はこの作品で芥川賞を受賞している。かすかな、そして頼りない記憶を踏まえて話すと、それまでの地に足のついた作品とはすこし雰囲気が異なり、どこか浮遊した不思議な要素が盛り込まれているのが特徴である。というのも、タイトルのとおり「熊」がひとつのキーワードになっているのだが、はちゃめちゃな熊の登場の仕方なのである。熊が、熊が︱︱。早々に記憶の限界がきた。想像以上に早かった。観念して『熊の敷石』(新潮社・二〇〇四年)を開く。こんな書き出しだ。「いつのまにか迷い込んだらしい陽の落ちる直前の薄暗い山のなかで、突然、人工芝みたいに固く、ところどころへんに骨張っていて、しかも同時にやわらかい不思議な下草がしきつめられている道に出た。近くに獣道でもあるのか、ほのかな生き物の匂いと体温すら感じられるこんな場所にぶつかったのはまさしく不幸中の幸い、疲れ切って言うことをきかなくなっている脚でもなんとか前に進めそうだし、最悪の場合このあたりで火を熾こして一夜を過ごそう。」なんにもわからない。
そういえばはじめて読んだ堀江敏幸の作品が「熊の敷石」だったことを思い出して、当時の自分をすこしかわいそうに思う。ファンタジー小説のような、冒険小説のような、異世界に迷い込んでしまったかのような描写。彼は身の回りの世界をじっくりゆっくり書く人だと聞いていたから、なおさら混乱した記憶が蘇ってくる。なにも掴めないまま手探りで進むと、「そう心に決めた瞬間、地面ぜんたいが巨大な黒い毛虫の絨毯みたいにざわざわうごめいて足もとをすくわれ、尻餅をついた身体を間断なく突きあげる褶曲運動がはじまったので、私は恐怖と驚きのあまり疲労も忘れて木々のあいだをやみくもに走り、気がつくと小高い岩場に駆けあがっていた。」と書かれている。ひといきで読むには少々苦しい一文を追いながら、いったいこれはどんな状況なのだと頭を抱えたその瞬間、「奴」はやってきた。「肩で息をしながらほんの数刻前まで楽園のように感じていた草場を見下ろすと、あのやわらかい真っ黒な道に大きな瘤が突き出て奇岩城と化し、さらに目を凝らせばおびただしい数の熊が両の脚でたちあがったまま身体を寄せあいへしあい帯状に連なって山の奥へ移動しているではないか。」出た、熊だ、そうだ、こんなふうにして熊が出てきたのだった。「猫町」の猫大量発生を読んで思い出したのは、この光景であった。
しかしここからがまた、自分の記憶の情けないところだった。てっきりわたしは、この熊大量発生こそが、「熊の敷石」のクライマックスだと思い込んでいたのだ。なんということだろう、始まって二ページにして、すでに熊が登場してしまった。堀江敏幸のことだから、「猫町」の語り手のように、散歩をしたり夢想にふけったり、そんなくだりがあるような気がしていた。きっとほかにも共通する部分があるだろうと。なにもかもが勝手な思い込みであった。このあと物語は︱︱あえて、なぜ冒頭で熊が現れたかには触れないでおく︱︱ノルマンディー地方の小さな村を訪れた日本人の語り手と、そこに住むユダヤ人の旧友のやりとりを追いながら進む。もちろん、こちらが物語の中心である。ひさしぶりに会った二人は思い出話に花を咲かせながら、それでもそれぞれの今を取り巻く、家族や友人、仕事の話で盛り上がる。盛り上がるといっても、静かな盛り上がりだ。互いの人生を確かめるように、でも深入りはせず、適度な距離感を保って。
最後まで読んでけっきょく、「猫町」との共通点は、熊大量発生だけであった。物語の本筋すら覚えていない自分の記憶を嘆きつつ、こうやってもう一度「熊の敷石」を読むきっかけを得られたことを嬉しく思おうと、前向きになってみる。だってこの機会がなかったら、わたしは「熊の敷石」を、たくさん熊の出てくる物語だと、思い込んだままだったのだから。