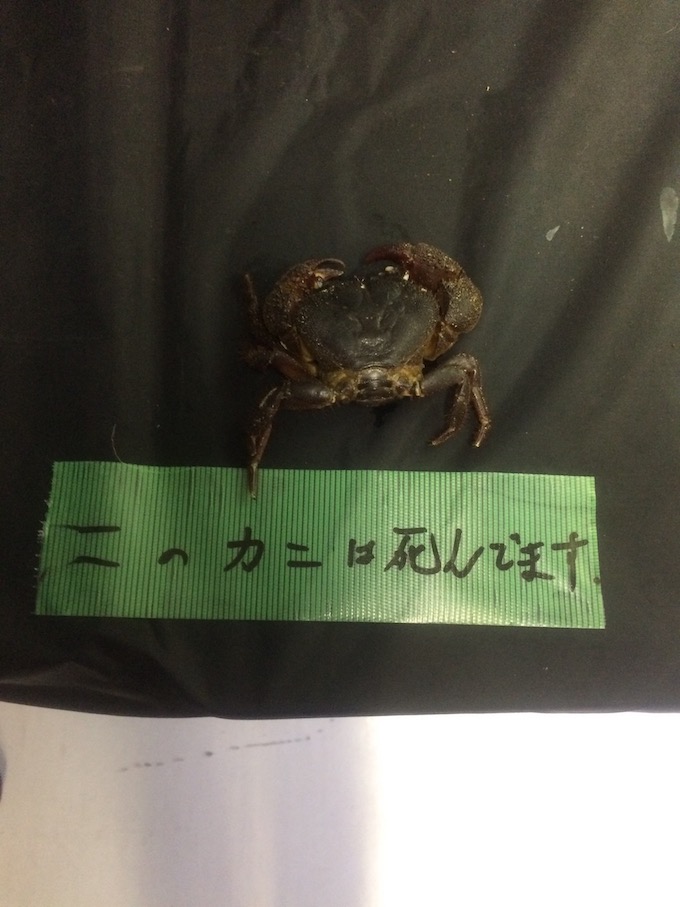猫大量発生、熊大量発生と来たからには熊猫――パンダ――大量発生小説を紹介したいところだが、あいにく思い当たるものがない。ので、同じ白黒可愛い系動物、ペンギンでご勘弁願いたい。そして安心してほしい、森見登美彦『ペンギン・ハイウェイ』(角川書店・二〇一〇/二〇一二)は、ちゃんとペンギン大量発生が本筋である。
郊外の新興住宅地に住む主人公のアオヤマ君はたいへん頭が良い。いつも持ち歩いている方眼ノートに日々のあれこれを書き留めている。結婚相手だって決めている。「ぼくはまだ小学四年生だが、もう大人に負けないほどいろいろなことを知っている」。
森見登美彦といえば京都を舞台に狸が出たりろくでなし男子大学生が黒髪乙女に恋をしたりというのがお馴染みだから、小学四年生の、しかも一人称の語り手とは意外だ。たぶん舞台も京都じゃない。
そんなアオヤマ君がペンギンを初めて見たのはある五月の朝。「風が吹き渡ると、朝露にぬれた草がきらきら光った。キウキウキシキシと学校の床を鳴らすような音が聞こえてきた。広々とした空き地のまんなかにペンギンがたくさんいて、よちよちと歩きまわっている」。アオヤマ君は猫や熊の目撃者のように恐れたり驚いたりはしない。研究者だから。「ぼくはしっかりと観察するために、そばに行くことにした。それが本当にまじりっけなしのペンギンなのかどうか、あるいは遺伝子に突然変異を起こしてずんぐりむっくりしたカラスなのか、それを研究する必要があったのだ。ほかの子どもたちは見ているだけ。ぼくが草を踏みしめる音と、風が電線をゆらす音と、ペンギンらしいものたちが立てるヘンテコな音が聞こえるばかりだ」。ペンギンが大量発生している光景に感情が反応するより先に、そもそもペンギンなのかペンギンらしいものなのか確かめようとしている。正体はともあれ、種類はあとから調べたところアデリー・ペンギンだった。「ペンギンたちが海から陸に上がるときに決まってたどるルートを「ペンギン・ハイウェイ」と呼ぶのだと本に書いてあった。その言葉がすてきだと思ったので、ぼくはペンギンの出現について研究することを、「ペンギン・ハイウェイ研究」と名付けた」。
研究者アオヤマ君は複数の研究を並行して抱えている。なかでも歯科医院のお姉さんの研究の占めるウェイトは大きい。毎週カフェでチェスを教えてもらいながら、ノートに書いたことをお姉さんに教える。おっぱいを見つめているのを指摘されたりしながら。ある日、謎めいていて中性的な雰囲気のお姉さんが「ペンギン・ハイウェイ」と関係していることが判明する。というのも、ペンギンはお姉さんが生み出していたのだ。お姉さんの投げたコーラの赤い缶が、ふいに白いものにおおわれ、いったん白くなった部分が泡立つように見えたと思うと黒く変色、はじけるようにして真っ黒な翼が側面から飛び出す。全体はさらにふくれ続け、回転を続けるうちに高度を下げ、先端がまるみを帯び、クチバシができ、ばたばたと翼を動かすような仕草をしながら、バスターミナルの中央へ着陸して、ころころころがる。「それが「ペンギン誕生」の瞬間であったのだ」。ペンギンの謎に、ペンギンを生み出すお姉さんという謎が重なる。「お姉さんは言った。「この謎を解いてごらん。どうだ。君にはできるか」」。
アオヤマ君と仲間のウチダ君、ハマモトさんがガキ大将のスズキ君の妨害にあいつつ仮説と検証を繰り返し(本作は日本SF大賞受賞作)人間的にも成長していく過程や、お姉さんとペンギンの謎のちょっと切ない解決といった物語もさることながら、アオヤマ君の語りに垣間見える少年らしさがなんとも微笑ましいのが魅力的だ。きらきらキウキウキシキシよちよちばたばたころころ。擬態語はひらがな、擬音語はカタカナという国語教育の是非が時折ネットで話題になるが、アオヤマ君はきっちりルールを守っているのかもしれないなんて想像するとニヤニヤ、じゃない、にやにやしてくる。
ところでペンギンは「人鳥」とも書くらしい。きっとアオヤマ君も市立図書館で調べてノートに記録したんだろうなあ、と思いつつ、猫・熊と字面が合うのでにやにやしながらタイトルに入れました。