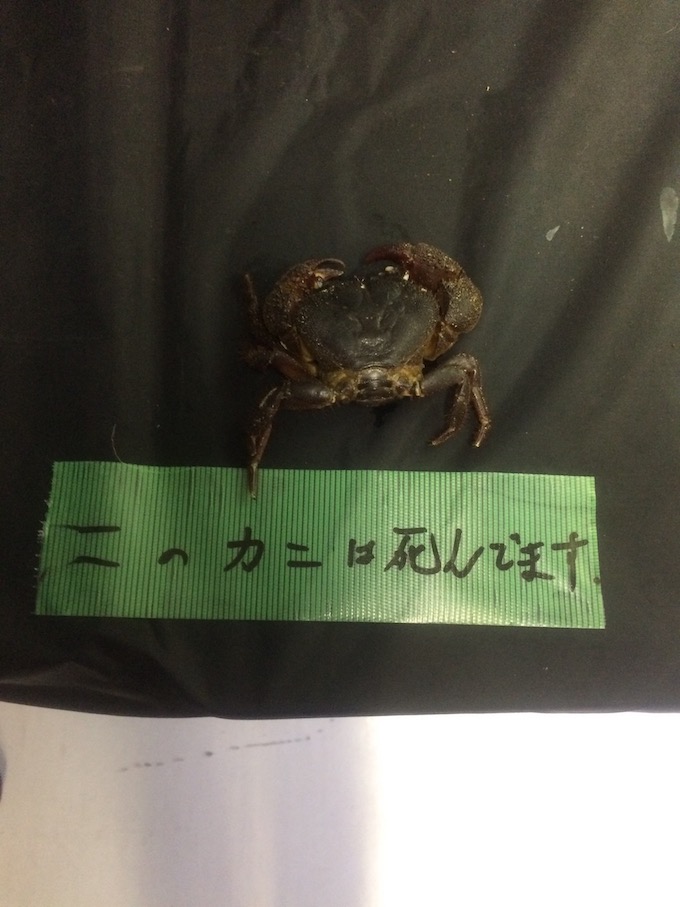「読者」は自明の存在ではなく近代化の過程で「成立」したものであることを前田愛は示してくれた。ところで実際にある人が「読者」になるには、当然のことながらある本がその人のもとに届く必要がある。誰かが書いた文章がそのまま「はい、これね」と言って直接誰かに渡されたとしたら、それは本ではなくて「私信」というもので、渡した人は著者じゃないし読み手も読者ではない。「著者」とか「読者」といったものは「本」の存在によって初めて成立するもので、本は様々な工程を経て工業的に生産される商品なのである。と同時に、著者と読者という二人の間には様々な思いを抱く「人」がいて、本を作ったり届ける仕事をしているわけだ。
『本を贈る』はそんな「著者以外」の人たちによるエッセイ集だ。編集者・装丁家・校正者・印刷・製本・取次・営業・書店員・本屋、そして最後に批評家の計十人が、自らの来歴や仕事内容に触れながら、「本を贈る」というテーマで思うところを自由に書き綴っている。
この本の面白いところは、出版関連業の中の人たちが自分の本への愛を披瀝するといったような単純な愛書家発・愛書家経由・愛書家行きの本ではないという点だ。
ウェブで読める本書の編集後記にはこう書いてある。「図らずも受け取ってしまったものを、そのままに独り占めにできないから他の誰かにパスをする。それが本づくりであり、本を売るということではないか。であるなら、本が書かれ、つくられ、届けられるプロセスを、本がひとからひとへと連続的に贈られる、贈与のプロセスとしてとらえてみたらどうだろうか。すでにそのことを意識的に実践しているひとに聞いてみたい。そう思ったことから、この企画ははじまりました」。「連続的に贈られる」ということは、校了ゲラが印刷へと渡ること、印刷されたものが製本へと渡ること、製本されたものが取次へと渡ること、それぞれ次の工程への受け渡しを「贈与」として捉えていることになる。本書の書き手は確かに贈与を意識して仕事に取り組んでいるが、だからと言っていま手元にある本がそういう贈与の連続で成り立っていなければいけない、ということなのだろうか? 「本は特別なものじゃない」と題した加藤製本・笠井瑠美子氏の文章は、「贈る」という言葉の熱を冷まして、私たちが気後れせず手に取れる温度にしてくれる。
「製造現場の人間が皆、出版事情に詳しくて、用紙に愛情を持っていて、慈しむように本を積んでいる――という理想風景を読者の皆さんは期待されるかもしれないけれど、本などとるに足らないものだと、何も特別なものではないのだと、そういう態度で本をつくり続け、そして買ってもらったほうがいいんじゃないか。本に興味のないひとも現場にはたくさん混ざっていて、でもそれぞれに仕事をきちんと果たし、俺の仕事は酒を飲むためにある! とかいって、仕事を続けられる。それはこれからは贅沢な考え方になってしまうのかもしれないけれど、本をつくったり売ったりすることが、世の中の数ある仕事のなかで、普通に誰でもが選べる職種であり続けてほしい。そうあることが、買うひとをも選ばないことに繋がっている気がするし、そうでなければ、子どもの頃の私に、本は届かなかったと思うのだ。」
『本を贈る』というタイトルなのに、そもそも誰かに物を、しかも本を贈るというのは難しいし苦手だと何人も書いているのは象徴的だ。そんななか笠井氏の文章は、本は贈りもの「としてある」のではなく、読者が出会ってしまって何かを受け取って初めて贈りもの「になる」ということを気づかせてくれる。そしてそういう状況のありがたさを教えてくれる。この視点から見れば、本書には大きく分けて、「他でもないこの本が贈りものになりますように」「作り/届けた本が贈りものになりますように」という二つの、排他的ではないモチベーションが描かれている。それぞれの工程ごとのグラデーションで交じり合いながらこの二つが共存して初めて、私たち「読者」の手元に本は届き、「読者」が成立するのだ。
ある本を「受け取ってしまった」ときに密かに完了される「贈与」のプロセス。その複雑さを覗き見できる贅沢を受け取ってしまった。