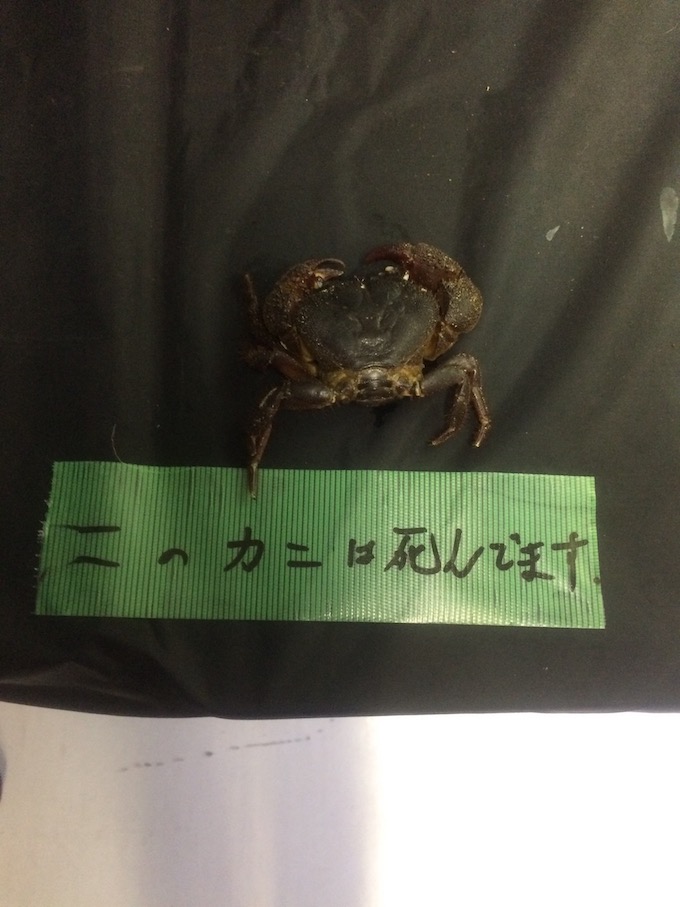坂口安吾のエッセイを集めたもので、大和出版から出た『生きよ堕ちよ』という本がある。これの解説で奥野建男はあけすけに、「もちろん安吾の小説は巧みではない。不器用であり、失敗作も多い」(二四九頁)と書いている。もちろん安吾はエッセイの方が面白いのである(ちなみに私のオススメは『風流』)。
そんなツマラナイ方の小説のなかでも、『海の霧』は一見すると地味でツマラナイ。まずもってタイトルからして湿っぽいし、「部屋も体躯も妙にドロドロと湿つぽい」と一人称の語り手自身が言っている始末。ジメジメを通り越してドロドロというのだから相当である。安吾研究でも、初期作品を論じる上で言及されることはあっても、この作品単体を考察した論文というのはほとんど見ない、というか筆者は見たことがない。
ではどうしてわざわざ取りあげるのかというと、私は安吾の短編小説のなかではこの『海の霧』が何故だか最も気に入っているのだ。筋というほどのものもないが、一応解説しておく。主人公「僕」は、四六時中指やら頭やら踵やらが痛いと嘆いては自分を罵ってくる「鮎子」と、どこか海辺の街で暮らしていた。死にたくはないが、絶望している。生活を変えたい、何処かへ行きたいと互いに言っていた二人はやがて、電車で新橋に行くのだが、どうもその頃から「鮎子」は「僕」を憎んだり軽蔑するようになる。尊敬の裏返しじゃないかと「僕」は思うのだが、そのうちどうやら二人は別れたらしい。「尊敬は恋愛の畢りなり」。
なんだそれは、解説になっていないじゃないか、だいたい新橋に行ったのは何が目的なのだ引っ越しか、と思われる向きもあろうが、実際お話は本当にこれだけなのである。五節に分けられてはいるが、別段大きな出来事が起きるわけでもないので起承転結もない。それでは何が気に入ったのかと考えてみるに、ひとつには、「どろどろ」でも「泥々」でもなく、「ドロドロ」なところではないか。というのも、この『海の霧』という作品には「ドロドロ」や「フワフワ」のようなカタカナ繰り返しのオノマトペが夥しい数出てくるのである。例えば筆者のMac Book Pro 13インチで青空文庫の『海の霧』を開くと、第二節の冒頭三段落がちょうど一面に表示できるのだが、この三段落の間だけで、カタカナ繰り返しオノマトペは実に七種類も出てくるのである。ついでに言えば「ヂッと」というのも凝視るのと考えるのとで二回出ていて、これはひょっとする安吾の語彙力が乏しいのではと思うと、どうもそんな簡単なことではない。
雨の日に、矢張りボヤけた黄昏がきた、僕は殆んど無意識に湿つた洋服を着込んでしまふ。部屋も体躯も妙にドロドロと湿つぽい、そして黴れた玄関に、なぜだか僕はヒソヒソと靴を結んで立ち上ると、急にソワソワと白らけた不安がこみあげてくる、足や手が一度にイライラと騒ぎ初めて、ひたすらに収拾し難い混乱が一瞬僕を絶望へまで導いてしまふ。ふと幽かに、羽搏きに似た何か物音が、耳を澄せば棟の何処かに、繁くバタバタと聴え初める、暗い廊下の片隅に、たとへば濡れた壁の中から誰か知らない金切声が頻りに僕へ叫びはじめる。
「僕」は夜毎酒場へ通って有り金すべてコニャックに代えてしまうというから、まあたぶんアル中である。引用の「ふと幽かに」以下など幻聴に他ならない。そういう人の不安の感覚を形容するに、三人称の語り手であればある種分析的に描写する必要がある。神の眼に対して口が子どものように「グショグショ」とか「タラタラ」とか言っていたら釣り合わない。ところが『海の霧』の場合語り手は一人称であり、病的不安を抱えている当人に分析的思考ができていたら、これはこれでオカシイのである。となれば最も伝わる表現はこのカタカナ繰り返しオノマトペではないか。日本語は外来語を用いないのであれば漢字とひらがなだけで完結できる以上、カタカナの存在はかなり目立って見える。『海の霧』ではカタカナ表記の外来語は本文に六種類、ルビに出てくる場合が五種類(「船員」に振られている、本文にもそのまま出ている「マドロス」を入れれば六種類)と決して多くはない。オノマトペに用いられるカタカナは、異化とは言えないまでも、有標なのである。また、オノマトペすなわち擬態語・擬声語は「擬」の字が使われているように、様態や音声の感覚印象を模したものである。つまり、感覚に訴える。このカタカナ繰り返しオノマトペの強迫的な反復は、読む側にも迫ってくるものがある。要するに、ドキドキするのだ。
いとうせいこうはこのようなカタカナの「反復の横溢」をもって、『海の霧』を処女小説『木枯の酒倉から』とともに初期ファルスに数え入れている(「安吾のカタカナ」、『坂口安吾全集14』月報「Mélange」所収)。念のため言っておくと、このファルスは精神分析等で言うphallusではなく、笑劇、道化を意味するfarce、ファースのことである。ちっとも笑えそうにないこの『海の霧』がファルスなのかはともかくとして、『木枯の酒倉から』の終盤、「聖なる酔っ払い」にして「蒼白なる狂人」の独白も、カタカナ繰り返しオノマトペが執拗に反復され、質は違えど先の引用同様に狂気を醸し出している。
と、尚も俺はフラフラと、ひどく陽気に歩き出し、クサを踏みわけて幾度も転げながらあのパゴダ――行者の御尻です――に辿りつくと、呪われたる尻よ、とこれを平手でピシャピシャと叩いたのだ。すると行者は尚も幻術に無念無想で、股にもぐした丸顔には例の脂汗とニタニタが命懸けにフウフウと調息しているのだった。
――余は断じて尊公の尻を好まんよ。
と、俺も詮方なくニヤニヤと空しい尻に笑いかけながら尚暫く叩いていたが、やがて退屈して酒樽へ戻ろうと足のフラフラを踏みしめて叢の中へわけ入ったのだが――(ああ、これも呪うべき行者の幻術であろうか)叢に秘められた階段に足踏みはずして、酒倉の窖へ真っ逆様に転り込むと、何のたわいもなく、俺は気絶してしまったのだ――。
こちらには町田康なら「はは、やれん」と書き足しそうな気持ち良さがあるとはいえ、カタカナ繰り返しオノマトペの濫用は『海の霧』になっても変わらない。『海の霧』は酔っ払い小説でもあったのだ。
オノマトペの使用と並んで、もうひとつ特徴的なのは、主人公の「僕」がひたすら何もわからないことである。「自分でも良くは知らない何か思案」、「何時の頃何処の記憶か知らない」、「何処へ行くのだか知らないが、僕はとにかく出発しやう」、「破裂とは如何なる結果を意味するか、それが僕には分らない」、頻出する「不思議」……。一応は物語の山場と言える四節も、「永い雨の二週間、僕の奇妙な緊張は、不思議な速力で育ち初めてゐた」で始まり、奇妙で不思議では何もわからん。だが、オノマトペと相まって心理描写が非論理的・感覚的であるだけ一層、海辺の風景描写が際立って美しく現れてくるのである。海が喚起する青、霖雨が喚起する灰色や黒、それと対照的な晴れた浜辺に映えるペンキや石畳の白……。暗に明にイメージされる色彩の印象が、ドロドロフワフワしてアイマイな主人公の心象に対して、時に調和、時に乖離しつつハッキリ浮かび上がってくるのである──。ちょっとカタカナが過ぎた。
この小説、永い雨の二週間で六月が過ぎて七月が来たというから、舞台は梅雨である。低気圧で頭もぼんやりするこの時期、無理して乾こうとせず、ドロドロした高湿度の小説に浸りきることこそ梅雨を満喫する術かもしれない。