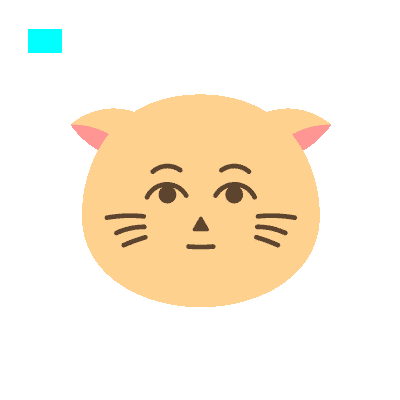2019年4月、平成8年に生まれた私が、その一時代の終わりを目前に、初めて自発的に本を読んだ。自ら進んで本を手に取り読み切ったことは、これまで一度もなかった。
タイムラインに流れる主張に嫌気が差す。それでもこの指はスワイプを止めない。人間関係に嫌気が差す。それでも人との関わりは断てない。すべきことがこなせない自分に嫌気が差す。それでも身体は机に向かわない。私をどこかに連れていってくれないだろうか。それは普段、私にとってはルノアールの喫煙席とホットココアと隣席で繰り広げられるマルチ商法の勧誘が担う役割だが、そんな定年後の甘党の日課は今の私を何も変えてくれなかった。もっと、自ら別の世界に没頭する必要があった。その答えがルノアールの喫煙席とホットココアと、本だった。
借金を返済できなかった代償に〈僕〉は〈あのバス〉に恐ろしいどこかへ連れ去られる。〈僕〉の願いは〈あのバス〉が来る前に、交際している5人の恋人に別れを告げること。すべきことがこなせない代償に、どこかへ連れていってもらいたい自分と、角度を変えつつも重なるその世界に、私は惹きこまれた。大きく違うのは〈僕〉に恋人が5人いるところだろう。今の私の恋人の数を何倍しようと5人にはならない。
実際、〈あのバス〉で連れていかれる以前から、〈僕〉はアブドーラ・ザ・ブッチャーを凌ぐ体格をした何もかもが規格外のブロンド髪の女性、繭美に見張られながら、同時に交際していた5人の女性それぞれに別れを告げにいくのだから、既に現実とはかけ離れたような世界に暮らしている。そんな中で繰り広げられるショートショートとも思えるようなテンポ感のいいエピソードは、初めて本を読む私でも飽きることなく読み進めることができた。各章が女性一人ひとりとの別れが描かれた本作は、それぞれが同じような構成で(一部の台詞は殆どの章を通して同じものが使われながら)成り立っている。この作品以降、数冊の本を読んでから振り返ると、その構成だけ見れば、読者に退屈さえ感じさせても仕方ない非常に挑戦的な構成だ。それでも、頁をめくるごとに少しずつ物語に厚みが増し、張り巡らされた伏線が回収されていくその様に、読書の素人ながらに伊坂幸太郎の技量を感じさせられた。
本は、タイムラインから逃れ、人間関係から逃れ、すべきことから逃(少し手を休めて離)れさせてくれる。私の読書は、この一冊から始まった。